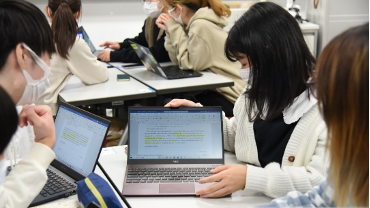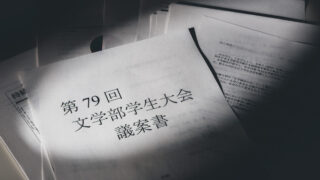京都市と大津市にまたがる「琵琶湖疎水(そすい)施設」で、トンネルなど5カ所が国宝に指定される見通しとなった。
重要文化財に指定される24か所の施設のうち、5か所が国宝になる見通しだ。近代の土木構造物としては、初めての国宝となる。
文化庁の文化審議会の答申では、「明治日本における都市基盤施設の金字塔である」と高い評価を受けた。
 国宝・重要文化財に指定される施設一覧=京都市上下水道局提供
国宝・重要文化財に指定される施設一覧=京都市上下水道局提供琵琶湖疏水は、明治維新において衰退の危機に瀕した京都の復興のため、1890年に建設された。
琵琶湖疏水の完成によって、琵琶湖から京都へ運ばれてくる水は、水道、水力発電、舟運、かんがい、防火用水、庭園用水など多目的に利用され、京都の経済や産業、文化を発展させた。
第一隧道は大津市域に位置する大津開門及び堰門、大津運河を経て、最も上流のトンネル。全長2,444mと当時日本最長の隧道であったことから、工期短縮のため、トンネル工事としては日本で初めて竪抗工法を採用した。
 第一隧道の様子=京都市上下水道局提供
第一隧道の様子=京都市上下水道局提供南禅寺水路閣は、蹴上船溜から分岐し東山の山裾を北上する分線が南禅寺境内を通過する箇所に設けられた、煉瓦造の14連アーチを用いた延長93mの水路橋。
 南禅寺水路閣の様子=京都市上下水道局提供
南禅寺水路閣の様子=京都市上下水道局提供これまで琵琶湖疏水施設は、年に第1疏水関連施設の12か所が国の史跡に指定され、2007年には、経済産業省により近代化産業遺産として認定された。
琵琶湖疏水記念館(京都市左京区)で資料研究専門員を務める吉田武弘さんは「この機会に、蹴上インクラインで写真を撮るなど疎水に関する面白いポイントに触れると同時に、歴史も学んでほしい」と話した。
 琵琶湖疏水記念館=6月9日、京都市左京区
琵琶湖疏水記念館=6月9日、京都市左京区(今井)
.png)