■議題2「R2030後半期計画に向けた議論の進め方について(論点提示)

【立命館・伊坂副総長】
学生一人一人が、さまざまな成長機会に参画してもらい、他者や社会との関わりの中で各自のパーソナルベストを更新してもらいながら、挑戦し続ける人材となってもらい、自らの目指す進路やキャリアを実現してもらいたい。学生の成長実現実感ナンバーワンの大学になりたいということを目指している。
(学生の学びと成長の実感について)自己省察の機会、あるいは自己理解の機会を他者からのフィードバックを通して得られて、他者理解と他者との中での自己の相対化の理解ができるようになった時に、成長を感じたと(懇談会で)指摘された。
「イノベーション・創発性人材」の育成に向けて、自分自身が学びの可視化、自己省察の深化を促しながら、学習者自らが主体的に創造することを目指す「コンピテンシー・フレームワーク」=①=を、25年度から試行的に運用できるよう進めている。
①コンピテンシー・フレームワーク 人的支援とシステム的な支援を適切に組み合わせることで、学びの可視化、自己省察の深化を促し、学習者が自らの成長を主体的に創造することを目指すもの。立命館は「学びによって伸張する資質・能力」をコンピテンシーとして定義。「命を立てる」をコア・コンピテンシーに、Resilience(しなやかさ)やInitiative(自発性)、Teamwork(チームワーク)など8つのコンピテンシーを設定した。
連続性のある学びの機会をどう整えていくかをしっかりと考えながら、R2030後半期に向けて、学生一人一人の学びの軌跡を把握できるようにした上で、次のチャレンジにつながる活動機会の情報をレコメンド形式で何とか提供できないのか、DX(デジタルトランスフォーメーション)の上手い活用の仕方の中で、学生の成長の機会の提供ができないか、その中で学生、院生の皆さんの自律的な学びが生まれるようなことを進めていきたい。
学生の皆さんの様々な活動を支援するのは当然重要な我々の使命だ。成長する機会やチャレンジする機会を作っていくための新たな学生支援の在り方をさらに深めていきたい。
未来の大学づくりに向けて、大学が学生、院生の皆さんとの対話と議論を積み重ねることを通じて、社会共生価値を創出する大学を目指していきたいと考えている。

【立命館・松原副総長】
学年歴について、現行の15週授業から14週授業に転換する。土曜日の授業を解消するとともに、学事日程に「ゆとり」を持たせることで、学生の多様な学びを一層促進する狙いがある。
学生の多様な学習機会を創出し、学生の成長を促進する契機として、各学部・研究科教学の特性に応じた、新たな教学展開とともに、学生・院生のさまざまな主体的な活動を後押しするなど、教育のより一層の充実につながることを期待している。
加えて、教員の研究機関の確保や社会貢献活動などへの移行と創出にもつながり、これらが学生の教学に還元されてくるだろうと考えている。
グローバル教養学部を除く全ての学部で、R2030における英語教育改革の改革方針が検討された。検討結果は、ピアーと名付けた新たな英語教育カリキュラムへ再編するという学部が3学部、また既存の英語教育プログラムの改革が12 学部だ。
文学部、理工学部、食マネジメント学部、総合心理学部では、2026年度に向けて英語教育カリキュラムの改革を進める予定だ。意欲の湧く授業を英語教育科目においても浸透させてくことを目指して、継続した議論を学友会と重ねていきたい。

【立命館・徳田副総長】
今後も学外の公募事業獲得に向けた努力を継続し、本学博士課程学生の経済支援の充実を目指していきたい。在籍する大学院生は質、両共に大きな転換点を迎えており、経済的支援の在り方についても、限りある予算を最大限有効活用していくため、質、量両面での検討が重要だと考えている。
次世代研究大学の実現に向けて、院生の研究環境や学習環境の高度化は不可欠なものであり、院協と学園側の連携は中核をなすものであるという考えに同意する。院生協議会との継続的な議論交換には、積極的に参画していきたい。

【立命館・山下範久常務理事】
本年度より大阪いばらきキャンパス(OIC)H棟の竣工、情報理工学部・研究科と映像学部・研究科の移転に伴い、社会共創の取り組みを本格化させてきた。
大学の組織として、社会競争のプラットフォームを整備し、社会や学生の皆さんに対して可視化し、連携先を積極的に開拓することによって、社会共創の可能性は大きく広がったと考えている。
マイクロソフトやアドビの教材ワークショップなどを活用したスキルの習得▽各種のプログラムによる社会課題の理解▽問題解決プロセス、グループワークなどの経験の習得▽企業や自治体との共創によるビジネスや地域課題の深い理解▽学生自身が構想する企業アイデアのブラッシュアップや実装化――など、可能性は無限大と言っていい。
大事なことは、こうした仕組みへの学生や院生の皆さんの主体的な参画だ。何ができるか自体を、学生、院生の皆さんに考えていただくという文化を確立する環境を我々としてはご用意したい。
社会共創はOICにとどまらず、全キャンパスに広がりを持つと考えている。衣笠キャンパスでは、デザイン・アート学部の開設を機に、全学生が利用できる「Fab lab(ファブラボ)」=②=を27年度に設置する予定だ。BKCでも、Fab lab機能を備えたスタートアップを推進する「グラスルーツ・イノベーションセンター」が25年度に開設する。
社会共創の仕組みを今後、衣笠キャンパスやBKCにも展開していきたい。
②Fab lab レーザーカッターや3Dプリンターなどのデジタルファブリケーション機器を活用したものづくりを支援する場。2024年4月にはOICのH棟にファブラボ「KOBO」がオープンした。
.png)
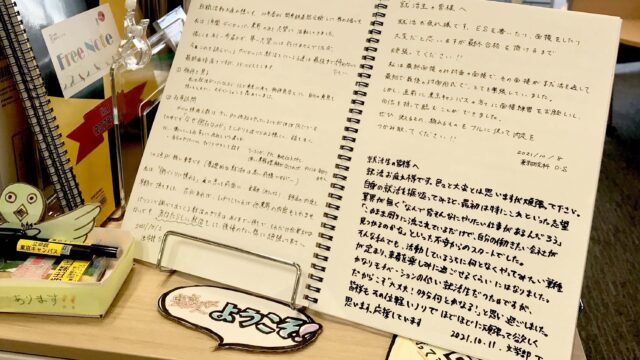

@4x-640x360.png)

