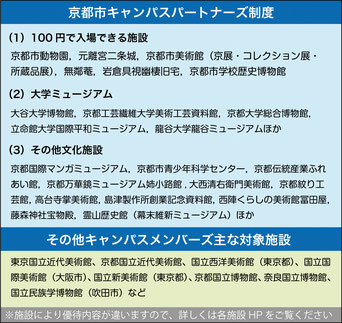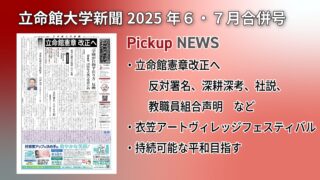◆「対話」で将来の平和の準備を
「未来を信じ、未来に生きる」を掲げる立命館の「未来志向」は否定しない。だが立命館憲章の改正案が、より良いものになっているか疑問だ。
改正案の解説では、学園の姿を未来志向に据え、留学生の立場でも理解しやすい表現にしたと説明している。立命館は、グローバル化で世界の各地域から学生・教員を受け入れており、構成員が大きく変わってきているのは間違いない。
しかし第2次世界大戦を巡る文言を削除すれば、未来志向になるわけではない。グローバルな学生・教員がいる立命館は、今の世界の戦争、平和にどう貢献するのかを示すべきだ。
 君島東彦・国際平和ミュージアム館長
君島東彦・国際平和ミュージアム館長そもそも立命館が「平和と民主主義」を教学理念に掲げた背景には、東アジアの平和を破壊した大日本帝国の侵略戦争がある。大学は戦争を止めることができず、むしろ戦争に加担した。大学の責任はなくなったわけではない。
現在は過去と地続きであるため、未来も過去と地続きだ。きちんと歴史に向き合う必要がある。なぜ戦争になったのか考え、どうすれば防げるかを考えることが求められる。
教学理念「平和と民主主義」を絶えず再確認・再定義し、その時点の社会状況に応じて中身を深めていくべきだ。
戦争は過去の話ではない。ウクライナやガザなどで、今進行しているのだ。これらの問題に日本の学問はどう対応するのかが問われている。
グローバル化した学園がグローバルな戦争と平和の問題に、留学生たちと共にどう取り組むかが書かれるべきだろう。
◇ ◇ ◇
私が平和を考える出発点は、啓蒙思想家のイマヌエル・カントだ。『永遠平和のために』にある平和の定義を、私は「国家間の一切の敵対関係を終わらせること」と訳したい。平和は関係性の概念なのだ。
過去の植民地支配と戦争で生まれた東アジアの敵対関係は、克服されたのだろうか。今の東アジアの敵対関係を終わらせること、平和構築が我々の課題だ。和解が実現されたのか自問自答しなければいけない。
国交がある国とは、一定程度和解したともいえるだろう。だが、市民の心の中で和解はなされたのか。まだ道半ばだろう。
 国際平和ミュージアムの常設展示(国際平和ミュージアム提供)
国際平和ミュージアムの常設展示(国際平和ミュージアム提供)国際平和ミュージアムの展示は、敵対関係がなぜあるのかを示している。平和博物館には被害者の側から被害を展示するものが多い中、国際平和ミュージアムは、被害と加害の両面を見つめている。きちんと歴史に向き合い、どのように敵対関係を克服しうるのか、考える材料を提供している。
立命館には多くの留学生がいる。留学生との日々の対話は、間違いなく平和を準備している。大学は平和外交の主体として極めて重要だ。
多様なバックグラウンドを持つ学生と接し、対話すること、とりわけ留学生と出会うことは、平和構築において大きな意味がある。生身のいろいろな人たちと出会うことが、将来の平和の準備であり、平和外交なのだ。
(聞き手・小林)

.png)