立命館大学新聞のコラム欄「海神(わだつみ)」。記者が日々の思いを語ります。

私の興味関心は常に「自分」から始まっていた。
「生まれ変わったら男になりたい。家庭を持ってもバリバリ仕事したいから」。中学生の夏、何げない会話の中でそう答えたことをよく覚えている。母子手帳にある、「育児が辛いと感じることがある」というチェック項目。チェックを見つけ、当時の母を想像したこともある。
悲しくて、怒りが湧いて、「ジェンダー」に興味を持った。社会学を勉強しようと思った。児童虐待、地域社会、多文化共生と、関心は広がった。視線は「自分」から「社会」へ移っていく。遠い誰かを想像するようになる。
「戦後80年」。テレビでも新聞でも、その言葉が飛び交う。特集を見て、過去と未来に、平和を祈る。
祖父はいつもラジカセを付けたまま眠る。幼い頃、「ヘンなの」と思いながら、横で目を閉じた記憶がある。祖母の葬儀前夜も、やっぱりラジカセは付いていた。また、「ヘンなの」と思った。「おじいちゃんは言わないけど、暗くて静かだと、やっぱりまだ戦争のこと思い出しちゃうんじゃないかな」。母がそう言った。
祖父が戦争を体験していることはもちろん知っていた。しかし正直なところ、戦争について祖父に尋ねたことはなかったし、尋ねようと思ったこともなかった。
「自分」と「社会」は分離したものではない。「社会」の中に「自分」がある。遠い誰かを想像しながら、実家から徒歩15分の距離に暮らす祖父には無関心だった。ラジカセを聞きながら、私は恥ずかしくなった。
(井本)
.png)


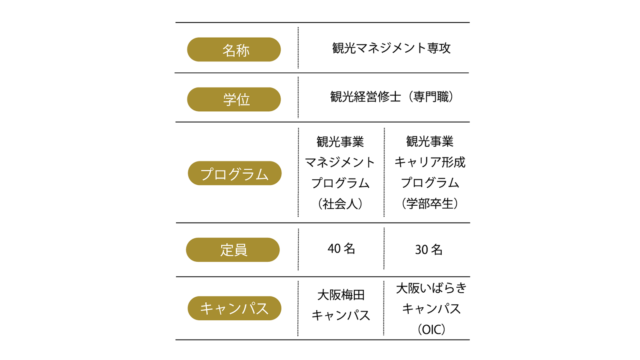
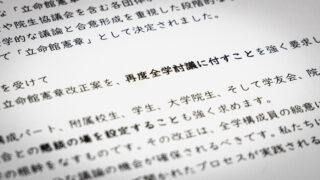
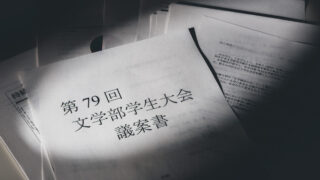
またしても左派メディア的な論調。ここまで革新的なのは珍しい。
大学新聞としての存続が懸念されている。