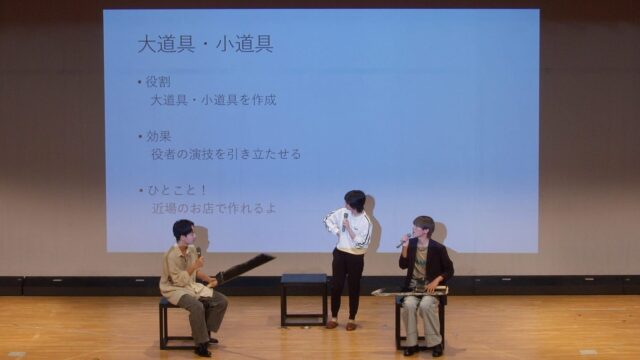【学友会・横尾中央常任委員長】
学園共創活動という言葉にはいまだ確実な定義がなく、この言葉が指すところには議論の余地がある。単に大学からの提案に対して意見を述べたり、追認したりするというような、議論に注目するだけの活動ではなく、学生の課題を解決するということに、焦点を当てた活動をさらに増やしていきたい。
課題解決こそが学生に対しての還元であり、学友会の存在意義・活動意義であると考えている。
2025年度以降の学友会と大学の議論においては、①2024年度のみならず、R2030前半期における課題を代表者会議において確認し、2025年度以降に改善へと進めていくこと②学園共創活動という言葉の持つ意味を捉え直し、共通の理解を持った上で、その意味に基づいた議論、懇談を行うこと③引き続き、多層的な議論の場を設定するとともに、その機会の確保及び議論内容の充実のために、学友会と大学の双方が積極的に注力すること――の3点を提起する。
25年度以降も引き続き、学生と大学が学園を共創するという方向性の下、学友会は今後も学園づくりにおける各種の政策に責任を持って携わること、携わるために活動を行っていくことをここに表明する。

【院協・開原会長】
(研究室の座席の)基準の見直しや個別の研究ニーズに応じたスペース拡充が必要ではないかと考えている。また施設利用の24時間化や遠隔地での図書資料利用の促進も不可欠だ。
具体的には、キャンパスアジア・プログラムや国際共同利用共同研究拠点といった既存の取組みを活用しつつ、研究室や共用スペースの利用環境を改善する必要性がある。
経済的支援の充実も重要なテーマだ。特に選抜型支援だけではなく、全ての院生が対象となる基盤型支援の拡充が求められる。物価上昇やインフレーションの影響を考慮した支援体制の整備がさらに必要ではないかと私たちは考える。
アカデミックポストの獲得を目指す院生には、教育プログラムの充実が必要だ。また企業就職を希望する院生に対しては、専門性に加えて実践的な能力や共働スキルが評価される支援プログラムを提供することで、多様なキャリアパスを支援する体制の構築が求められている。
院協としては現場の声を集約し、院生が直面する具体的な課題を共有する役割を引き続き担っていきたい。今後も(大学と院協の)共働体制を進化させ、院生一人一人の研究環境を豊かにし、学園全体の研究力向上を目指していきたい。
■議題2での意見交換

【教職員組合・松田特別執行委員】
本学の特徴として、非常に多様な学びの経験をされた学生が入って来られるところがある。新しい取り組みをやっていくと同時に、全体としてユニバーサルがボトムアップするにはどうしていくのか、ということを考えていく必要がある。
■まとめ・閉会

【立命館・仲谷総長】
(議題が)多方面であったがために、意見交換で終わって議論まで進んでない。問題意識は少なくとも共有できたと思っている。
次世代研究大学が浸透していないという問題意識がある。次世代研究大学は社会に対しての言い方で、学内向けには「ワクワクする大学・大学院をどう作っていくか」という話だと思う。そのためには学生、院生、教職員の皆さんとの共創活動が必須だ。しっかりこのことも協議していきたい。
学友会から「目前の課題が解決されないことには、より大きな目標に向けて活動することは難しい」とあった。相反するものではないという気がしている。次世代研究大学に関連する取り組みや課題が、学生の日常生活にどう表れているのかという見方をしてもらえると、捉え方が変わっていくと思う。
研究力のベースとしての探究力は、学部生の間に伸ばさなければいけない。探究力は何かというと、自らが選んだ課題・目標の実現に、主体的に取り組むような姿勢を持てるかどうかだと思う。
主体的にどう関わって、計画を立てて、実現していくかという能力が探究力だと思う。そこに専門性などいろんなものが加わって、研究力に上がっていくという考え方をしてもらいたい。
学生、院生、教職員が、R2030チャレンジ・デザインの推進を一緒になって行えるよう、私としても尽力していきたいと思っている。また、学友会、院協から発言があった課題をどう解決できるかについては、継続的に協議をさせていただきたい。
.png)