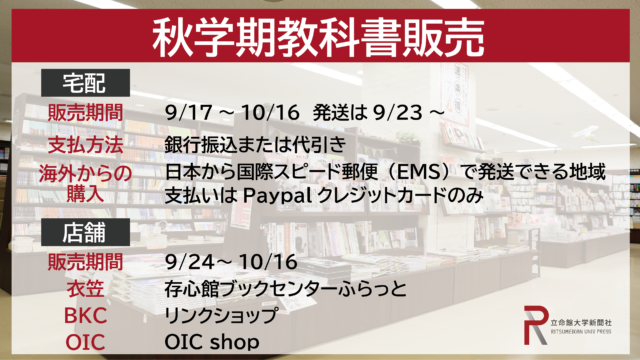今年の夏で終戦から80年。戦争を知る世代が少なくなる中、核なき世界を目指して京都で活動する学生がいる。持続可能な平和とは何か。節目の年に何を思うのか聞いた。
 倉本芽美さんは本学国際関係学部にて学ぶ4回生=6月22日、京都市北区
倉本芽美さんは本学国際関係学部にて学ぶ4回生=6月22日、京都市北区■抱いた違和感
広島出身の倉本さん。広島市内に出れば、核兵器反対運動に参加する人や、原爆ドーム(広島市中区)の前にキャンドルが灯される様子を見ることもあった。
本学に入り、核兵器の存在によって戦争を抑える安全保障政策「核抑止」について学んだ。「核兵器のない平和な世界を求めている人がいる一方、核兵器を平和をつくる手段として使っている人もいる」。ギャップに気持ち悪さを感じた。
考えが揺れるときもあるという。「核兵器はない方がいいと思う一方、もしかしたら核兵器に頼る平和がいいのかもしれない、と思わない訳ではない。だがやはり、核兵器に頼る平和は持続可能ではない」
「核兵器は、過去だけでなく今の問題」とし、「ただ非人道性のみで核兵器を否定するのではなく、国際政治の理論でも、核兵器について自分の言葉で語れるようになりたい」と話す。
核兵器は本当に持続可能な安全保障政策として成り立っているのか、という点に関心を抱くようになった。
 倉本さんは「核兵器は過去の問題ではない」と訴える=6月22日、京都市北区
倉本さんは「核兵器は過去の問題ではない」と訴える=6月22日、京都市北区■花垣さんとの出会い
倉本さんが、初めて出会った「名前と顔が一致する被爆者」。それが花垣ルミさんだった。1945年8月6日、爆心地から約1.7キロの地点で被爆した。
「自身が被爆者であることが、娘に何か影響を与えてしまったかもしれない」
倉本さんは、花垣さんが涙ながらに語っていたことを強く覚えているという。
「戦争を経験された方のストーリーは多種多様。だからこそ1945年8月のことだけでなく、その後の人生のことについてもっと知っていく必要があるし、もっと多くの人に聞いてほしい」
■次世代に求めること
被爆者団体の全国組織「日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)」は2024年、ノーベル平和賞に選ばれた。
受賞理由の一つに、日本被団協の活動が次世代に受け継がれている点がある。
その「次世代」とは誰なのか。倉本さんは、10代や20代だけでなく、直接的な原爆の被害を体験していない全ての世代を指す、という認識を共有していきたいと話す。
「戦争を体験していない世代が増える中で、どう語り継いでいくのかという問題がある。それは、原爆を経験した世代より下の世代にとって、共通の課題」とし、どの世代に対しても参画を求める。
■平和の在り方
「被爆者の体験が多種多様であるように、平和や核兵器に関してどのような点に関心を持つのかもさまざま」と話す。
多様な視点から核兵器の存在について問うていくことが、今の核軍縮を進める国際社会で行われている。
核兵器でいえば、その非人道性だけでなく国家の安全保障政策が決定するまでの過程、環境保全といった多様な問題が付随している。
「平和の在り方は人それぞれ」と話す。「戦後80年の今、それが持続可能な平和なのか、また、現在核兵器が実際に使われたらどうなるのか、各々が少し考える余地を持つ夏になれば」
 本学国際平和ミュージアムの地下での倉本さん=6月22日、京都市北区
本学国際平和ミュージアムの地下での倉本さん=6月22日、京都市北区(吉江)
.png)