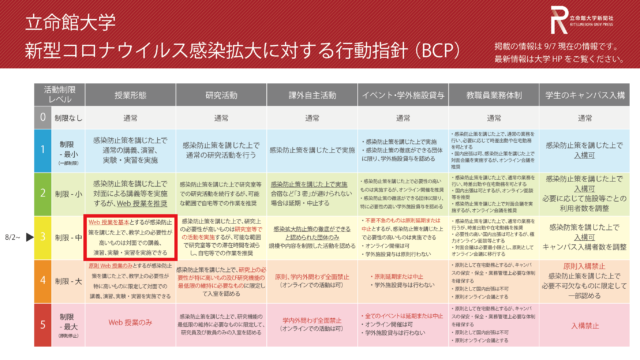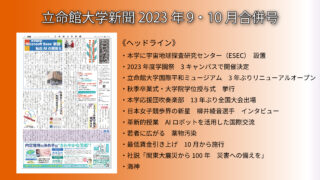若者の間で薬物汚染が拡大している。今年、大学生が違法薬物に関する犯罪で検挙される事例が相次いで発生した。東京都では7月、私立大学の運動部員複数名が大麻を所持したとして逮捕された。京都府内では7月までに私立高校の運動部の元部員ら複数名が同様に大麻所持で逮捕されている。全国的に大学生などの若年層を中心に大麻事犯の検挙数が増加しており「大麻使用は安全だ」という認識の拡大に京都府警は警戒を強めている。
 大麻取締法で規制されている乾燥大麻(京都府警提供)
大麻取締法で規制されている乾燥大麻(京都府警提供)■大麻事犯急増、過去最多へ
京都府警本部組織犯罪対策第3課(組対3課)の林祐彰警部によると、かつて日本における薬物事犯の主流は覚せい剤事犯であったが、近年は大麻事犯が急増しているという。全国の大麻事犯の検挙人員は2014年から増加が続いており、2021年には2014年の約3倍となる5482人にまで増加、過去最多を記録した。京都府内でも増加傾向にあり、2022年には過去最多となる159人が検挙されている。京都府内では今年に入って8月末までに大麻事犯の検挙人員は134人を記録しており、昨年と比較しても早いペースだという。しかしこれらの数値は、使用者全体から見れば「氷山の一角にすぎない」と林警部は話す。
_2D_2.png) 過去10年の京都府内の大麻事犯の検挙人員数の推移(出典:京都府警)
過去10年の京都府内の大麻事犯の検挙人員数の推移(出典:京都府警)大麻事犯は覚せい剤事犯よりも若者の比率が高いという特徴を持つ。今年、8月末までの大麻事犯で検挙人員に占める10代・20代の割合は73.1%に上る。林警部は若者の大麻使用のきっかけとして「友人からの誘い」が多いと話している。大麻事犯で検挙された人に対するアンケートの結果によると、初めて違法薬物を使用した際の動機として「好奇心、興味本位」が最多、続いて「その場の雰囲気」が多いという。林警部は大学生の薬物使用にも言及し「大学生の間で大麻がまん延しているという感覚はある」と話した。
■大麻特有の「ハードルの低さ」
若者を中心に大麻が拡大する要因について林警部は、SNS(交流サイト)の普及や価格の安さ、摂取の手軽さなどに加えて「大麻は安全だ」という誤った情報の拡大を挙げ、「大麻使用のハードルが低くなっている」と指摘する。
大麻は「ゲートウェイ・ドラッグ」と言われる。他の薬物よりハードルが低い大麻は、使用するとより強い作用を求めたり、売人などから勧められ他の薬物へと手を出すことから他の薬物の入口となる。大麻は使用すると酩酊感や陶酔感を味わえると言われている。しかし、大麻の使用は精神障害や知能指数の低下、幻覚や妄想などの副作用を引き起こすという。林警部は「大麻は他の薬物より害がなく、依存性が低い」「海外には大麻が合法な国があるため安全」といった誤解の拡大に警鐘を鳴らし「違法薬物が体にいいはずがない」と訴えた。
.png)