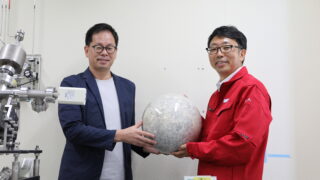今年3月に転覆事故が発生した「保津川下り」は、10月で運航再開から3カ月を迎える。事故では観光客を乗せた船が転覆し、船頭2人が死亡した。事故後初となる紅葉シーズンを前に、運航会社である保津川遊船企業組合(京都府亀岡市)は安全対策の周知に努めている。
 急流を下る保津川下りの様子=2021年11月14日、京都市西京区
急流を下る保津川下りの様子=2021年11月14日、京都市西京区保津川下りは、京都府亀岡市から嵐山(京都市右京区)までの桂川(保津川)を日本の伝統和船・高瀬舟で下る「川下り」。約16kmにわたる区間を1時間半から2時間かけて下る。ミシュラングリーンガイド一つ星に認証されており、外国人観光客も多く訪れる京都の観光名所として知られている。
コロナ禍前の2019年、保津川下りには24万人を超える観光客が訪れた。新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年には約9万6千人まで落ち込んだが、2022年には約19万7千人まで回復。2023年1月から3月の各月の乗船人数は2019年比で100%を超え、さらなる観光客の増加が期待されていた。
 コロナ禍の2021年、修学旅行生を乗せて運航される保津川下りの様子=2021年11月14日、京都府亀岡市
コロナ禍の2021年、修学旅行生を乗せて運航される保津川下りの様子=2021年11月14日、京都府亀岡市■転覆事故発生、運航停止に
3月28日午前11時ごろ、急流で知られるポイント「高瀬」において、保津川下りの船が岩に衝突して転覆する事故が発生した。この事故では、乗客25人と船頭4人が落水し下流に流され、乗客は全員救助されたものの船頭2人が死亡した。事故直後に現場で救助活動の指揮を執った、保津川遊船企業組合営業統括理事の豊田覚司(さとし)さんは「保津川下りが始まって以来の大きな事故だった」と当時を振り返る。
 保津川下りで使用される高瀬舟。最大乗船人数は30人、全長は10mを超える=10月10日、京都府亀岡市
保津川下りで使用される高瀬舟。最大乗船人数は30人、全長は10mを超える=10月10日、京都府亀岡市事故では、舵(かじ)担当の船頭が舵を空振りする「カラ舵」状態となってバランスを崩し船尾から落水。他の船頭が船尾に到達し航路の修正を図ったが、舵を正常な位置に戻せず岩に激突し転覆したと同組合は発表している。この事故により、保津川下りは運休を余儀なくされた。事故を巡っては、国の運輸安全委員会が調査を続けている。
 保津川下りの船(事故船とは無関係)。船体後部の棒状のものが舵=2020年3月25日、京都市西京区
保津川下りの船(事故船とは無関係)。船体後部の棒状のものが舵=2020年3月25日、京都市西京区事故の後、同組合に設置された事故対策本部では、舵持ちが落水したことや船が操舵不能に陥ったこと、緊急通報・救助要請に時間を要したことのほか、救命具が作動しなかったことが問題点として挙げられた。
保津川下りでは国土交通省の承認を受けたベルト型の救命胴衣を使用しており、手動膨張式と自動膨張式を併用していた。事故時に乗客が身に着けていた救命胴衣は、7人が自動膨張式であったのに対し、残り18人は手動膨張式。事故による落水時、自動膨張式は全て正常に膨張した一方で、手動膨張式では約半数の乗客が開くことができなかった。事故後、乗客に行われた聞き取りでは「手動の紐が分からなかった」「引っ張る余裕がなかった」などの回答があったという。
.png)


-640x360.jpg)